
目を背けたくなる現実も、眩しすぎる希望も、きっと君を強くする。
死と太陽は直視することは不可能である。
名言データ
0
いいね
0
コメント
この名言をシェア
この名言について
- 意味の要約
人間が直視できない、人生の根源的な真実。
- 背景・意図
この言葉は、私たち人間が、あまりにも大きすぎる、あるいは強烈すぎる真実に対して、真正面から向き合い続けることの難しさを教えてくれます。 「死」は誰にでも訪れる避けられない運命ですが、その事実を常に意識し、直視し続けることは、私たちの心にとって大きな負担となります。また、「太陽」は生命の源であり、絶対的な存在ですが、あまりにもまぶしすぎて、直接見つめれば目を傷つけてしまいます。 これらは、私たちの心の防衛本能のようなもので、自分を守るために、時に目をそらしたり、少しずつ理解しようとしたりする、人間の自然な姿を表しているのです。 この言葉は、そんな人間の限界と、それを受け入れることの大切さをそっと示唆してくれます。
- 現代での活かし方
もしあなたが、どうしようもなく辛い現実や、あまりにも大きすぎる問題に直面して、心が押しつぶされそうになった時、この言葉を思い出してみてください。 無理にすべてを直視しようと焦らなくても大丈夫です。時には、少し距離を置いてみたり、信頼できる誰かに話して、その光を和らげてもらったりすることも大切です。 完璧に理解しようとせず、自分の心の状態を大切にしながら、少しずつ、自分なりのペースで向き合っていくこと。そうすることで、きっと気持ちが軽くなり、前に進むための小さなヒントが見つかるはずです。
- 起源歴史上の発言
出典
関連する名言
名言の登録申請
このページに関する名言が見つかりませんか?
あなたの知っている名言を登録申請して、コレクションを充実させましょう。
あなたの知っている名言を登録申請して、コレクションを充実させましょう。



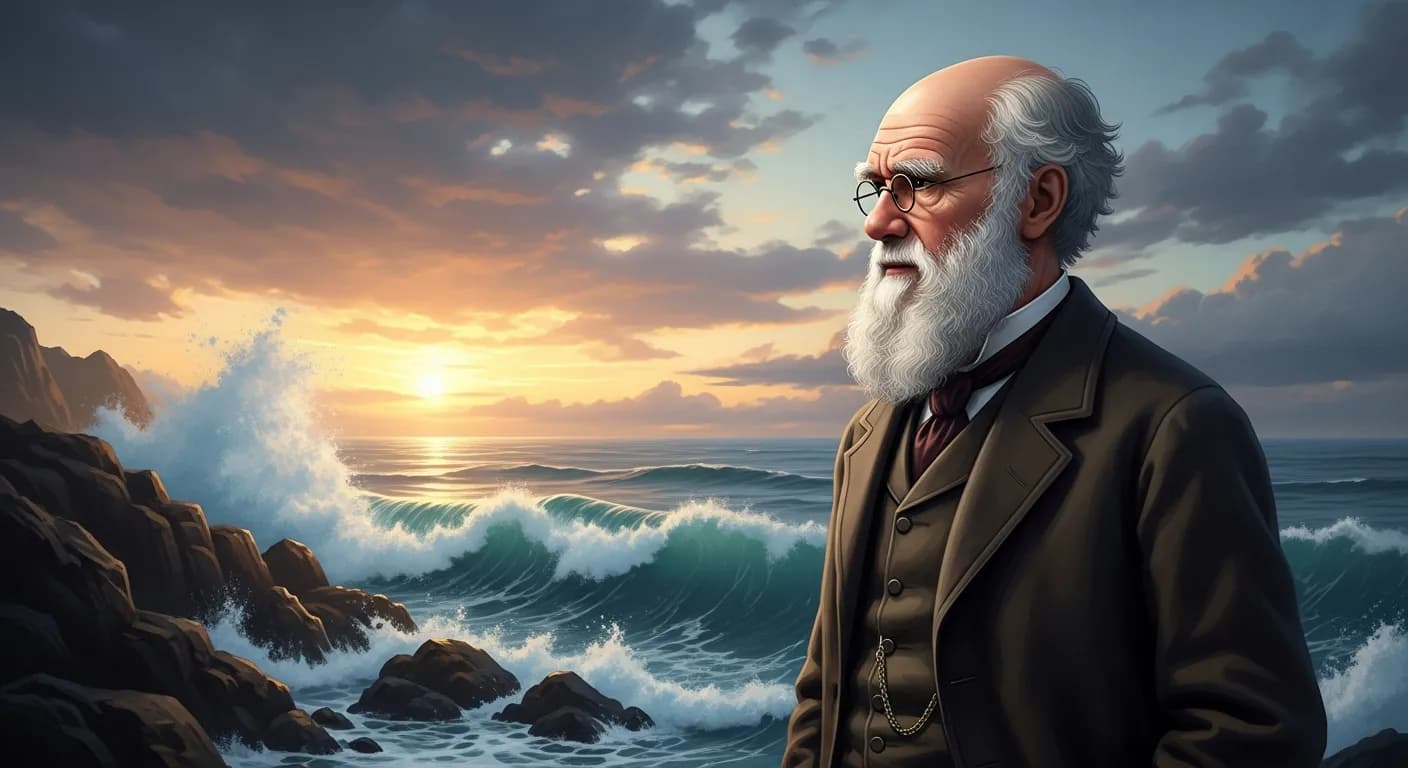
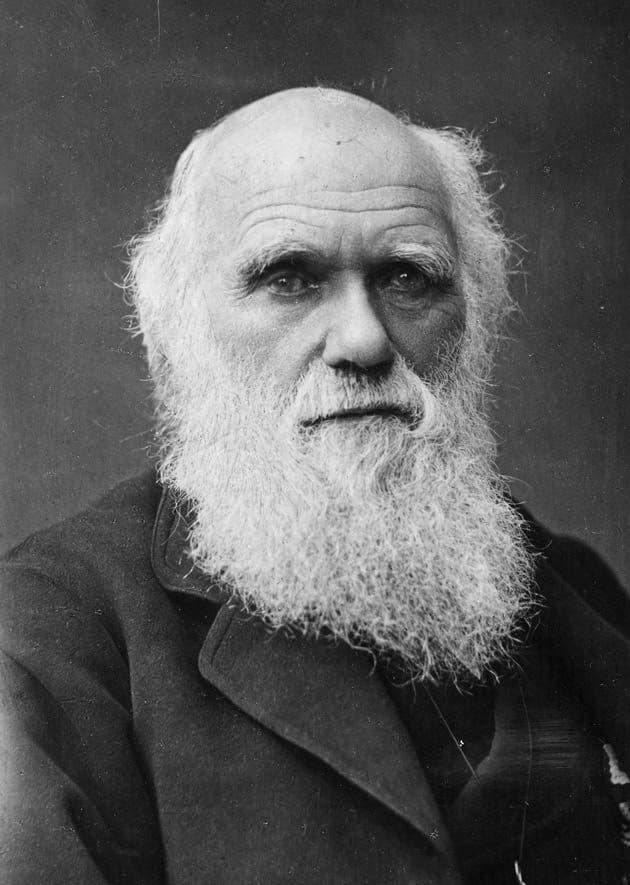




コメント (0)
コメントはまだありません
この名言についての最初のコメントを投稿しましょう。