
頭ではわかってる。でも、心が納得できない。そんな矛盾を抱えて生きるのが人間だ。
死は救いとは言いながら、そうは悟りきれぬものである。
名言データ
0
いいね
0
コメント
この名言をシェア
この名言について
- 意味の要約
死の救いを悟りきれない人間の本質。
- 背景・意図
「死は救い」という言葉は、苦しみからの解放や、輪廻転生といった宗教的・哲学的な側面を持つことがあります。しかし、私たちは感情を持つ生き物であり、大切な人との別れや、自身の存在の終わりを、頭で理解するようには受け入れられないものです。 この言葉は、そんな人間の根源的な感情と理性の間の葛藤を、静かに、しかし深く表現しています。どんなに理屈で納得しようとしても、心はそう簡単に割り切れない。それは、私たちが「生きている」証拠なのかもしれません。
- 現代での活かし方
この言葉は、私たちが何かを割り切れない時、そっと寄り添ってくれるでしょう。 頭では「こうすべきだ」と分かっていても、心がついていかない。そんな経験は誰にでもありますよね。 仕事で大きな失敗をしてしまったり、大切な人との関係に悩んだり。 そんな時、「死は救いとは言いながら、そうは悟りきれぬものである」という言葉を思い出してみてください。 無理に割り切ろうとしなくていい。自分の感情がまだ追いついていないことを、そっと認めてあげる。 そうすることで、少しだけ心が軽くなり、自分に優しくなれるかもしれません。
- 起源歴史上の発言
出典
関連する名言
名言の登録申請
このページに関する名言が見つかりませんか?
あなたの知っている名言を登録申請して、コレクションを充実させましょう。
あなたの知っている名言を登録申請して、コレクションを充実させましょう。


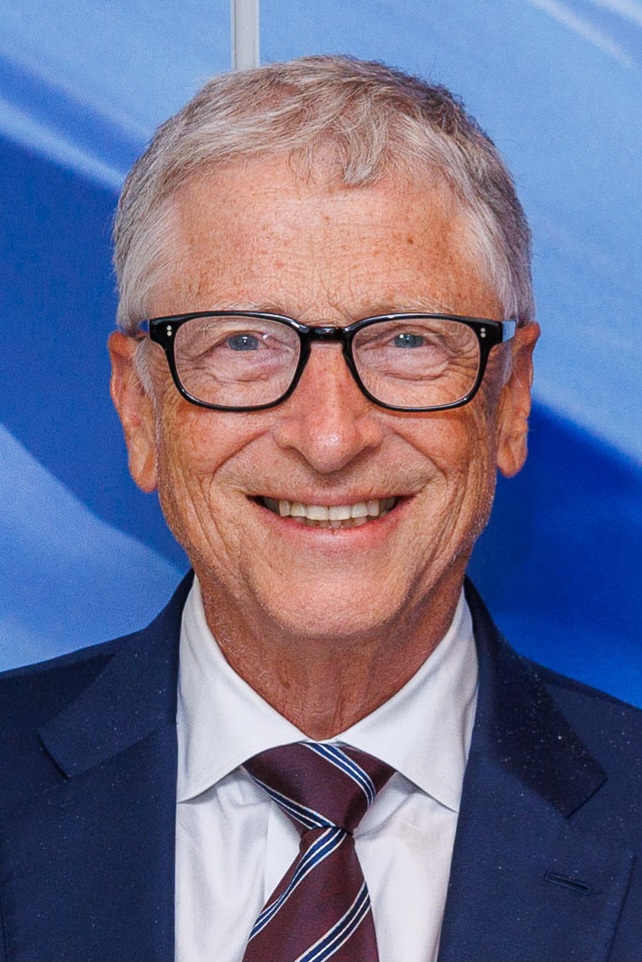
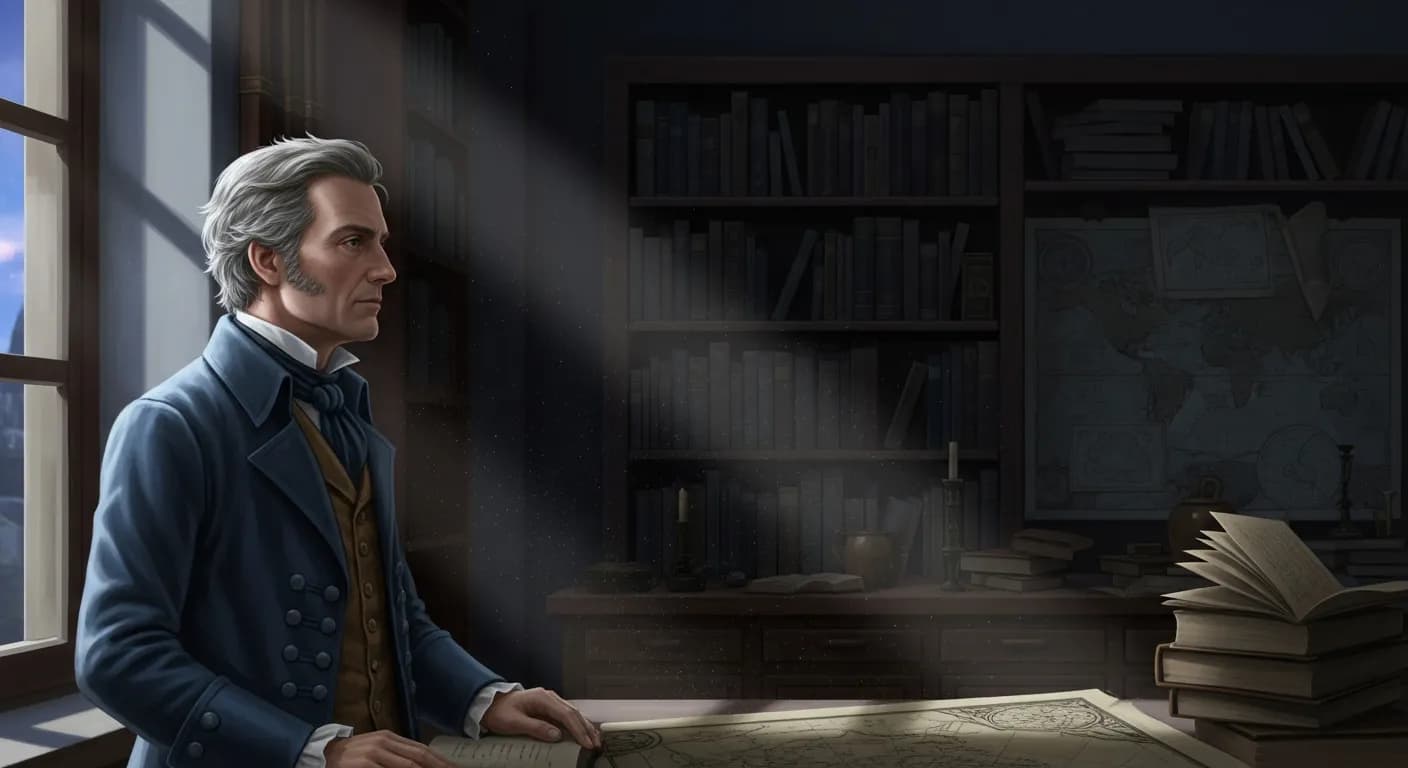



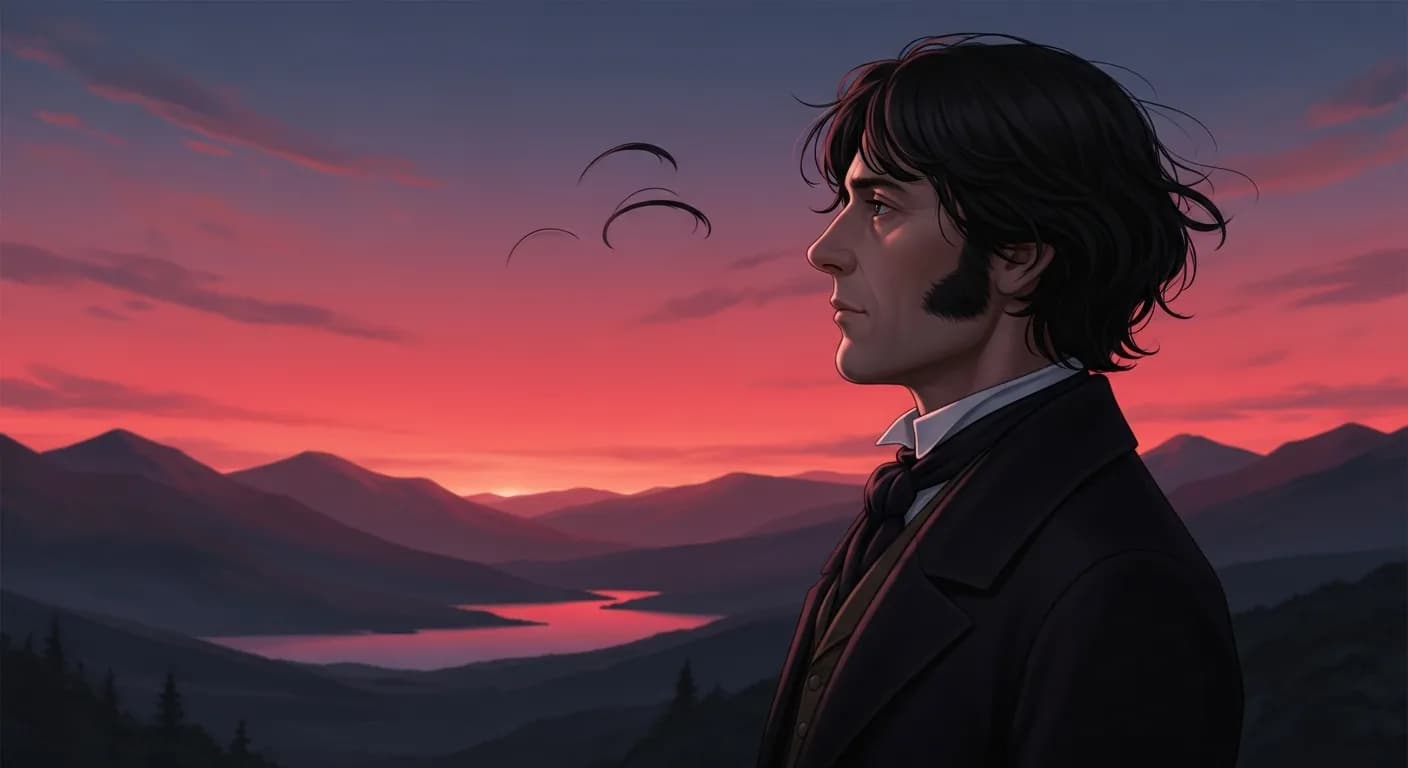

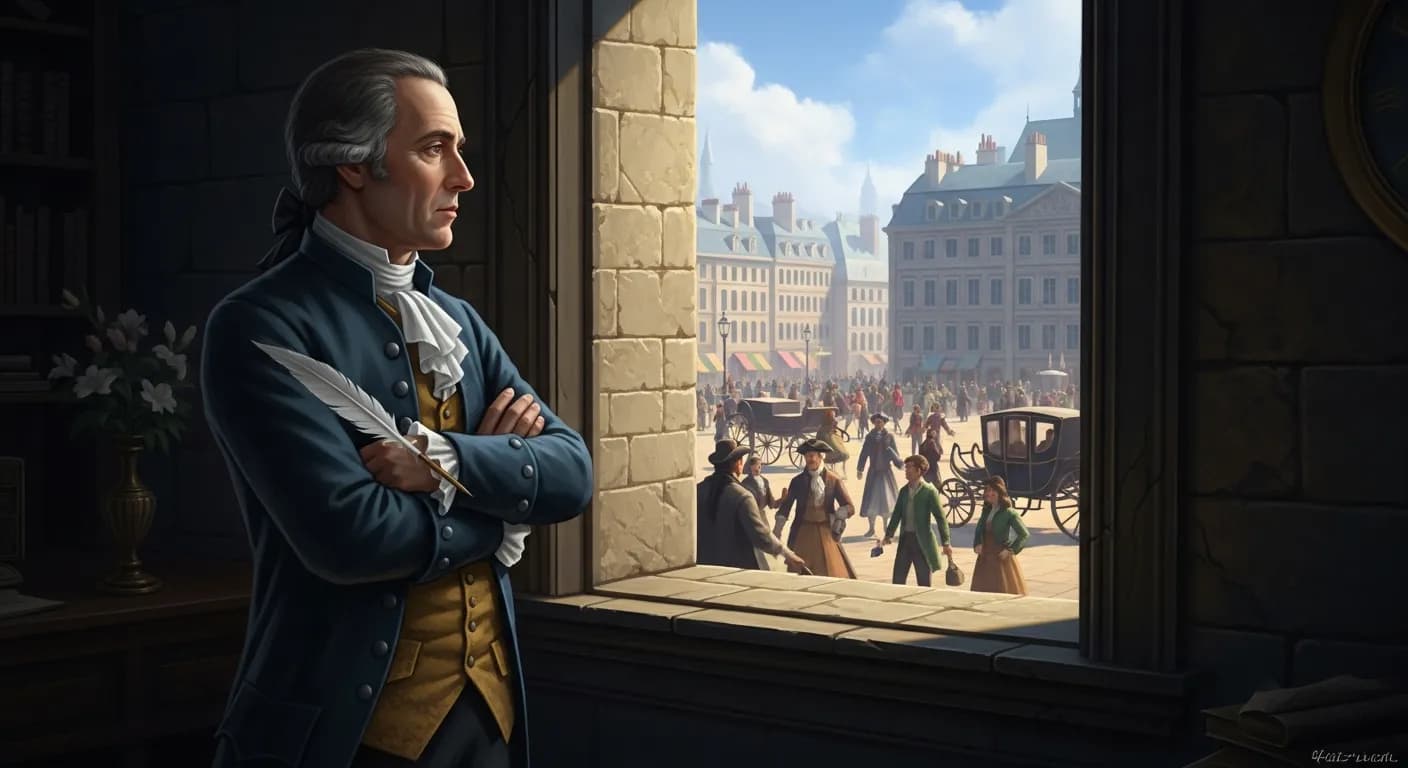

コメント (0)
コメントはまだありません
この名言についての最初のコメントを投稿しましょう。